SEOコンサルティングサービスのご案内
専門のコンサルタントが貴社サイトのご要望・課題整理から施策の立案を行い、検索エンジンからの流入数向上を支援いたします。
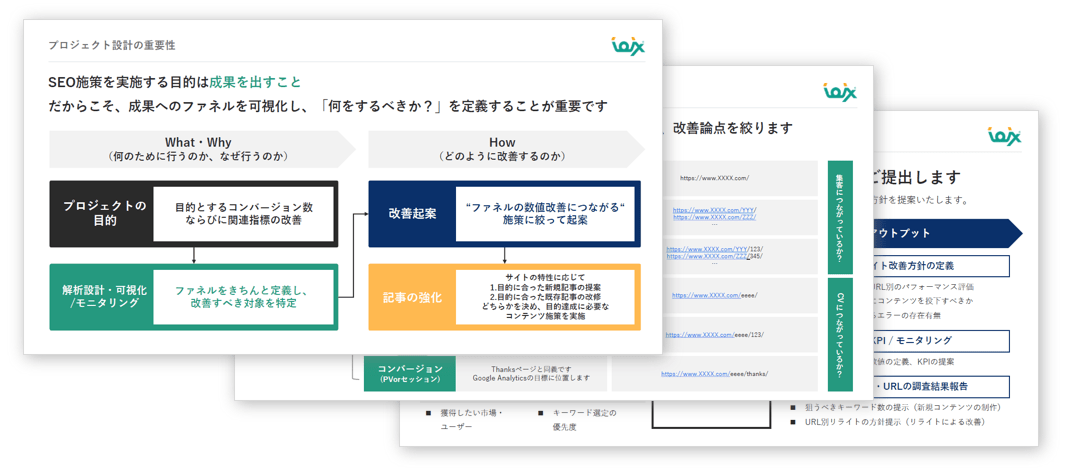 無料ダウンロードする >>
無料ダウンロードする >>
アルゴリズムとは計算や問題を解決するための手順・方法のことであり、SEOにおいてはGoogleの検索エンジンがWebページの検索順位を決めるためのルールを指します。
Googleの検索エンジンは、日々インターネット上の膨大なウェブページを巡回(クロール)し、内容を理解・分類(インデックス)しています。そして、ユーザーが検索を行うたびに、このインデックスされた情報の中から、アルゴリズムに基づいて最適なページを選び出し、ランキング付けを行っているのです。
Googleのアルゴリズムは200以上の要素を評価指標としてランキングを行っていますが、そのすべてが公開されているわけではありません。既存のSEOは、あくまでアルゴリズムの内容に対する推測、および実践の結果に基づいて行われています。また、アルゴリズムはつねにアップデートが行われ、より検索ユーザーの役に立つサイトが高い評価となるように改善が重ねられています。
目次
日本における検索エンジンのシェアはGoogleが約65%を、Yahoo!が約30%を占めています。そしてYahoo!の検索エンジンはGoogleのアルゴリズムを採用しているため、日本におけるSEOは実質的にはGoogle対策とほぼ同義になっています。
理由は以下の3つです。
インターネット上には数兆ページもの情報が存在します。その中からユーザーが必要とする情報を効率的に見つけ出すためには、機械的な判断基準が不可欠です。
ユーザーが知りたい情報に素早くたどり着けるよう、関連性が高く、信頼できるコンテンツを優先的に表示することで、検索体験の質を高めることを目的としています。
不正な手段で検索順位を上げようとするウェブサイト(スパムサイト)を排除し、公平で質の高い検索結果を維持するためにも、アルゴリズムは常に進化しています。
Googleは、検索結果のランキングを決定するために、200以上とも言われる多種多様な要素を組み合わせて評価しているとされています。それらの要素は日々進化し、AIや機械学習の導入によってさらに複雑かつ賢くなっています。
ここでは、特に重要とされる主要な評価要素をいくつかご紹介します。
最も基本的な要素であり、ユーザーの検索キーワード(クエリ)とウェブページの内容がどれだけ関連しているかを評価します。
第一にキーワードの含有です。ページのタイトル、見出し、本文に検索キーワードが含まれているか。ただし、単なるキーワードの羅列(キーワードスタッフィング)はスパムとみなされます。
次に検索意図の理解。Googleのアルゴリズムは、ユーザーがそのキーワードで何を求めているのか(情報収集、購入、場所の特定など)を深く理解しようとします。そして、その意図に合致したコンテンツを高く評価します。
例えば「コーヒー」と検索した場合、コーヒー豆の選び方を知りたいのか、近くのカフェを探しているのかなど、文脈を判断しようとします。
ユーザーにとって本当に価値のある、質の高い情報を提供しているかどうかが最も重視されます。
E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)は、Googleがコンテンツの品質を評価する上で特に重視している概念です。
Experience(経験): 実際にその製品を使った経験や、サービスを利用した経験など、実体験に基づいた情報が提供されているか。
Expertise(専門性): そのトピックに関する専門知識やスキルがあるか。
Authoritativeness(権威性): その分野における権威として認められているか。
Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で信頼できるか。サイト全体の安全性や透明性も含まれます。
上記のコンセプトを軸に、評価されるコンテンツがサイトには求められます。具体的には、網羅性・独自性(ユーザーの疑問を完全に解決できるほど情報が網羅されているか、他のサイトにはない独自の視点や情報があるか。)や、情報の鮮度(ニュースやトレンドなど、最新の情報が求められる分野では、情報が更新されているか)オリジナリティ・独自性などがあり、他のサイトからのコピーコンテンツや、AIによる自動生成コンテンツで質の低いものは厳しく評価されます。
ウェブサイトがユーザーにとって使いやすく、快適に利用できるかどうかも重要な評価項目です。
他のウェブサイトから張られるリンク(被リンク)は、「このページは価値がある」という推薦票のような役割を果たします。
被リンクには質と量の側面があり、単に数が多いだけでなく、権威性のある信頼できるサイトからのリンクであるかどうかが重要です。また、被リンクの多様性も重要です。様々なドメインからの被リンクがある、指示されているサイトであることが評価されます。
そして、アンカーテキストも重要な要素です。 リンク元のテキストが、リンク先のコンテンツ内容と関連しているかどうかを評価します。ただし、不自然なリンク構築(有料リンク、自作自演リンクなど)はペナルティの対象となります。
検索エンジンがウェブサイトを適切にクロールし、インデックスできるようにするための技術的な側面も重要です。代表的な観点は以下の3つです。
Googleのアルゴリズムは固定されたものではなく、より良い検索体験を提供するために日々改良が加えられています。特に大規模な変更は「コアアップデート」として知られ、検索順位に大きな影響を与えることがあります。
2025年7月現在の主要な動向としては、以下の点が挙げられます。
Googleは、GeminiなどのAIモデルを検索アルゴリズムに深く統合し、より高度な文脈理解とユーザー意図の把握を目指しています。これにより、キーワードの表面的な一致だけでなく、コンテンツ全体の意味を正確に捉え、ユーザーの疑問を解決できるかを重視する傾向が強まっています。
「体験」が加わったE-E-A-Tは、さらに厳格に評価されるようになっています。実体験に基づいた一次情報や、その分野の専門家による信頼性の高いコンテンツが、これまで以上に高く評価される傾向にあります。
Core Web Vitalsは引き続き重要であり、ページの表示速度や安定性など、ユーザーがストレスなくコンテンツを消費できるかが重要視されます。煩雑な広告やポップアップなど、UXを損なう要素はマイナス評価となる可能性があります。
低品質な自動生成コンテンツ、質の低いスクレイピングコンテンツ、期限切れドメインの悪用など、様々なスパム行為に対する監視と対策が強化されています。
Googleは、ユーザーにとって本当に「役立つ(helpful)」コンテンツを評価する方針を明確にしています。これは、検索エンジンのためではなく、あくまでユーザーのために作られたコンテンツが報われるという考え方です。
アルゴリズムは常に変化するため、「これをすれば必ず上位表示できる」という絶対的な対策はありません。しかし、Googleの根本的な目標は「ユーザーにとって最も質の高い情報を提供する」ことであるため、この原則に沿った施策を継続することが最も重要です。
アルゴリズム変動に左右されない、長期的なSEO戦略のポイントは以下の通りです。
サイト内の導線を分かりやすくし、ユーザーが目的の情報にスムーズにたどり着けるようにする。
SEOにおけるアルゴリズムは、複雑で常に進化していますが、その根底にあるのは「ユーザーに最高の検索体験を提供する」というGoogleの理念です。小手先のテクニックに走るのではなく、この本質を理解し、ユーザーにとって本当に価値のあるウェブサイトを作り続けることが、結果としてアルゴリズムに評価され、検索上位を維持するための最も確実な道と言えるでしょう。
現代のSEO担当者は、アルゴリズムを単なる「ブラックボックス」と捉えるのではなく、その意図を読み解き、ユーザーと検索エンジンの双方にとって最適なサイトを構築する「賢い羅針盤」として活用していくことが求められます。
SEO最新情報やセミナー開催のお知らせなど、お役立ち情報を無料でお届けします。
